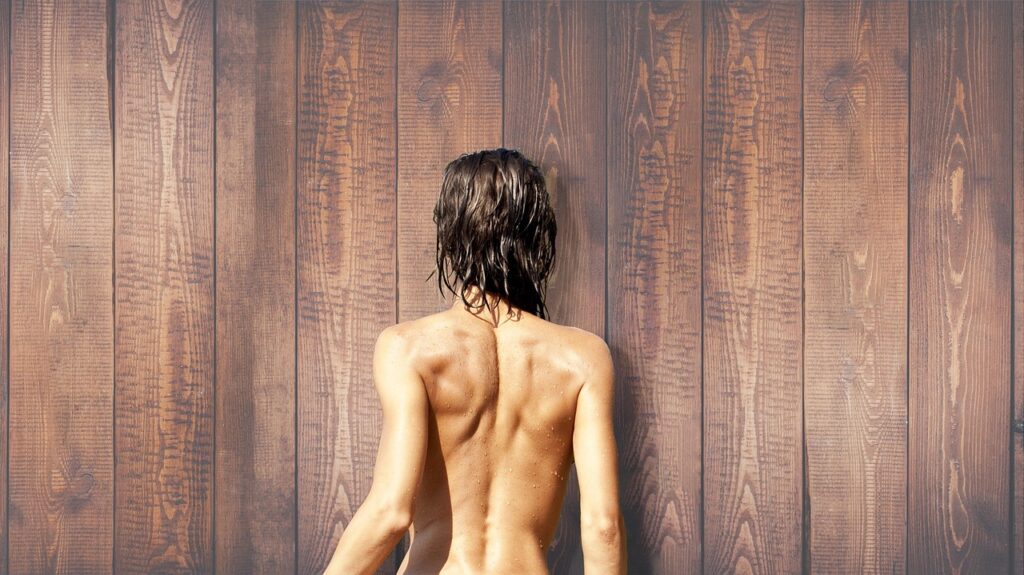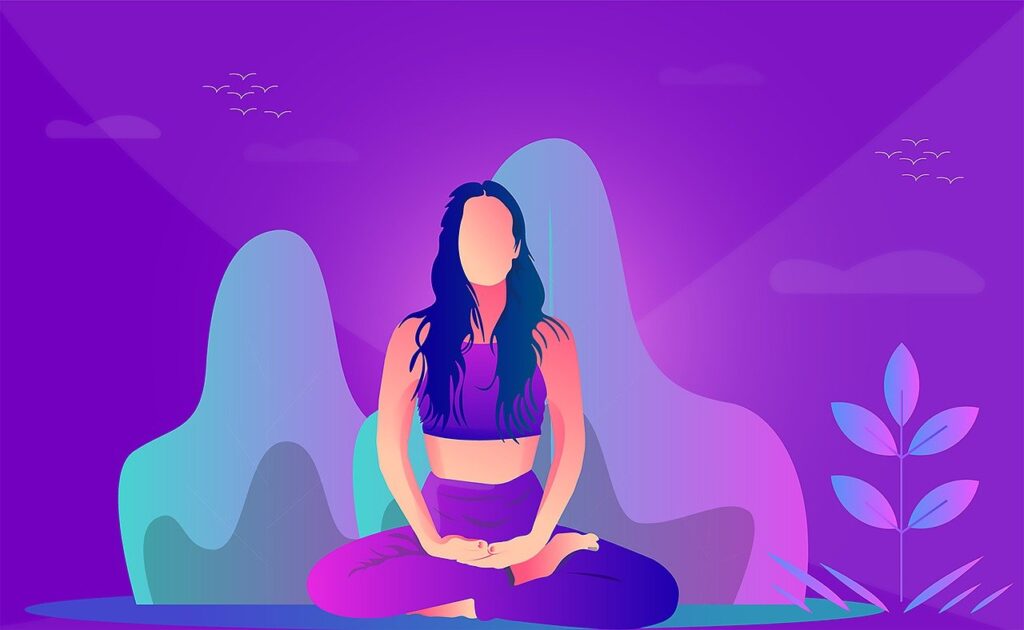そもそも自律神経が乱れるのは何故?
ストレス自律神経のはたらきとは?
自律神経とは、わたし達の体が生きていくために循環器、呼吸器、消化器などの機能を調節してくれる神経のことです。わたし達が意識しなくても心臓は動いて血液を全身に送り出し、胃は食べたものを消化して栄養を吸収、寝ている間でも呼吸を続けています。これはすべて自律神経のはたらきによるもので、24時間休みなく働いています。からだを動かしている自律神経は、交感神経と副交感神経の2つで構成されています。
●交感神経
主に昼の時間、体が活動するときに活発になるのが、交感神経。緊急時やストレスを感じた時にも、活発になります。心拍数を増やし、消化器の動きを抑え、血管を収縮させて血圧をあげる働きをします。主に激しい運動したとき、緊張、興奮しているとき、仕事に集中しているとき、危機を感じているときなどは、交感神経が優位になっているのです。
●副交感神経
体を休めているとき、夜に優位になるのが副交感神経。心拍数を減らし、消化器官を活発に動かし、血管を広げて血圧を下げて、体をリラックスに導きます。副交感神経が優位になることで、体をしっかりと休息させることができるのです。
自律神経の乱れはバランスの崩れ

自律神経を構成している交感神経と副交感神経は、お互いに協力して働いています。仕事を一生懸命行っているときには、体を緊張状態に持っていく交感神経が働き、体をリラックスさせる副交感神経はお休み。夜ゆっくりと眠るときには、副交感神経が優位になってエネルギーを回復させて、エネルギーを消費する交感神経はお休み。このように、一方の神経が優位になっているときは、もう一方の神経は抑えられる、というようにバランスをとっているのです。
しかし様々な原因により、この自律神経のはたらきのバランスが崩れてしまうことがあります。交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかなくなってしまうのです。そうすると休息したいのに交感神経が優位になったままで副交感神経に切り替わらず、寝付けない、熟睡することができない、といったことが起こってしまうのです。このように交感神経と副交感神経のバランスの崩れは、自律神経の乱れにつながっていくのです。
自律神経が乱れる原因とは?
自律神経が乱れてしまう原因は、主に次の3つのものが挙げられます。
●身体的・精神的なストレス
過労、事故、ケガ、季節の変わり目の気温の変化、音、光は私たちの体に身体的なストレスとなります。また仕事でのプレッシャー、不安、職場の人との人間関係は精神的なストレスとなります。これらのストレスが過剰になってくると、自律神経の乱れを引き起こしてしまいます。
●生活習慣の乱れ
夜更かしをして寝るのが遅くなる、朝になっても起きず昼過ぎまで寝ている、食事の時間が不規則、これらの生活習慣は自律神経の乱れを引き起こしてしまうことがあります。交感神経は日中体を動かすために優位になり、副交感神経は食事の時や体を休める夜に優位になるという、一定のリズムに添って働いています。そのため生活の時間がまちまちになってしまうと、自律神経の乱れを引き起こしてしまうのです。
●疾患が原因のこともある
更年期障害は女性ホルモンの分泌量の急激な減少により起こりますが、これが原因で自律神経の乱れを引き起こしてしまいます。自律神経失調症は、精神的・身体的ストレスにより自律神経が乱れて発症する病気ですが、その症状はさらに自律神経を乱れさせるという悪循環になってしまいます。
自律神経が乱れると起きる症状
自律神経は体の様々な部位のはたらきをつかさどっていますから、自律神経が乱れると体中にいろいろな症状が現れてきます。その症状には次のようなものが挙げられます。
●頭痛
女性に多い頭痛ですが、その原因に自律神経が深くかかわっています。
「緊張型頭痛」
頭痛の70%は緊張型頭痛といわれており、これは交感神経が優位になって肩や首、頭の筋肉が緊張することで、周りの神経を圧迫することで起こる頭痛なのです。
「片頭痛」
頭痛の約30%は片頭痛であるといわれています。片頭痛は血管が拡張して周りの神経を圧迫することで頭痛を引き起こすのですが、これにも自律神経のはたらきが関係しています。
緊張状態の時は交感神経が優位になっているのですが、この時に交感神経が優位になりすぎると、その反動で副交感神経が優位になった時に過剰になってしまいます。そのため血管を必要以上に拡張させて片頭痛が起きてしまうのです。そのため、副交感神経が優位になることが多い休日に、片頭痛に悩まされる人が多いようです。
●目
「眼精疲労」
仕事で忙しかったりすると交感神経が過剰に働きます。そうなると首や顔に筋肉が緊張するので、普段よりも血流の流れが制限されてしまいます。そのため、疲れを取るのに必要な酸素や栄養分が行き渡らなくなってしまいますので、目が疲れやすくなってしまいます。
「ドライアイ」
目に潤いを与えてくれる涙の分泌は、副交感神経の時に高くなります。それで交感神経が過剰に優位になってしまうと、目が乾燥しやすくいなるのです。
「めまい」
交感神経が優位の時は脳への血流が制限されてしまいますが、これは内耳の機能低下を引き起こしてしまい、めまいとなって表れてきます。
●胃腸
自律神経のはたらきは胃や腸の調子にも大きく影響を及ぼします。消化、吸収、排泄は副交感神経が優位の時に行われます。交感神経がストレスや緊張でずっと優位になってしまうと、胃腸のはたらきは低下。胃もたれ、胃痛、食欲不振、便秘といった症状が出てしまいます。また、胃腸の粘膜への血流の流れが阻害されてしまいますので、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんなどのリスクも高まってしまいます。
●耳
交感神経が過剰に優位になってしまうと、脳や耳への血流が悪くなってしまいます。これによって耳の機能、音を伝達する中耳、音を感じる内耳、音を脳へと伝える前庭神経の働きが低下、難聴や耳鳴りが起きてしまうのです。
●呼吸
呼吸は副交感神経が優位の時に深くなり、交感神経が優位の時には浅くなるのです。ストレスや疲れで交感神経が過剰に働くと、呼吸が浅くなってしまいます。そのため呼吸が早くなったり、ときには過呼吸を引き起こしてしまうこともあります。
●肩こり
交感神経が過剰に優位になると、肩や首周りに力が入ってしまいます。この状態が続くことで、肩こりを引き起こしてしまうのです。
入浴が自律神経を整えるのに効果的な理由

仕事でストレスを感じたり、緊張していると、自律神経の切り替えがうまくいかなくなってしまいます。そうなってしまうと、夜になっても交感神経が優位になったままで、眠れなくなってしまうことがあります。
そんな時に活用したいのが、夜の入浴タイム!この時間を上手く活用することで乱れてしまった自律神経を整えることができるのです。入浴が自律神経を整えてくれるのには、次の3つの理由があります。
お湯の温度
ちょっとぬるめかな、と感じる40℃くらいのお風呂に浸かるのが自律神経を整えるのにはおすすめです。体温より少し高い温度のお湯に浸かることで、血行を良くしてくれます。また体が芯から暖まりますので、新陳代謝が促進され体内の不要物の排出が促されますし、緊張して硬くなった筋肉を柔らかくしてくれます。
お湯の水圧
お湯に浸かると体は水圧の影響を受けます。お湯に浸かると水圧で横隔膜が上がり、肺の容量が減少します。これにより呼吸の回数が増え、心臓の動きが活発化。血流が良くなることで疲労物質を流してくれ、体の疲れを取ってくれるのです。
お湯の浮力
水には浮力がありますよね。水に入って体が浮力で浮くと、筋肉や骨、関節といった、普段体を支えている部分の負担が減るのです。また、筋肉が緩むことで体がリラックスしα波が出やすくなり、副交感神経を優位にしてくれます。
自律神経の乱れを整える入浴方法
自律神経が乱れて交感神経が活発になりすぎると、睡眠の質に大きな影響を与えます。そこで入浴を利用して体をリラックスさせることで、交感神経を落ち着かせて、副交感神経のはたらきを優位にさせましょう。自律神経を整えてくれる入浴に方法は、次の点に気をつけましょう。
適切なお湯の温度は?
自律神経を整えるための入浴法でまず気をつけたいのは、お湯の温度。大体39℃から40℃くらい、人の体温よりも少し高いくらいの温度がすすめられています。この温度の湯船につかると、一旦交感神経が優位になります。しかしそれほど温度が高くないので、徐々に体がこの温度に慣れていくのです。
どのくらいの時間、湯に浸かるのがいいのでしょうか?15~20分以上湯船に浸かるといいのだそう。湯温もそれほど高くありませんので、これでゆっくりと体を温めていきます。また入浴で体温を上げておくと、睡眠中に体温が低下しやすくなります。睡眠中に体温が大きく低下すると、睡眠が深くなり体の疲れも取れやすくなるのです。
いつ入浴するのが効果的?
自律神経を整えるという目的で入浴するなら、寝る1時間前には入浴を終えるのがいいでしょう。ベットに入る時間を22:00とするのなら、20:00から21:00には入浴を終えておくのがいいのです。これで副交感神経が優位なときに眠りにつくことができるので、寝つきも良くなりますし、疲労をしっかりと回復させることができます。
もちろん、入浴後1時間後にはベットに入るようにします。スキンケアなど必要なことをやったら、テレビ・スマホは見ないで寝るようにしましょうね。
自律神経を整えるのにさらにできること

湯船につかると水圧がかかるのですが、これはマッサージと同じような効果があります。湯船につかっているときにマッサージをすると、さらにこの効果をアップさせることができます。例えば足がむくみやすい人は入浴中に足をマッサージすることで、血流を良くし疲労回復、リラックス効果が期待できます。
また、入浴剤やアロマオイルを活用するのもおすすめ。炭酸入浴剤は、血管を拡張して血流を良くしてくれます。ラベンダー、オレンジスイート、スイートマジョラムといったアロマオイルを、湯船に数滴垂らしてみましょう。その香りで緊張していた気持ちが癒されるだけでなく、これらのオイルは入浴後にゆっくり、深く眠るのを助けてくれます。これらは副交感神経を優位にするのを助けてくれ、乱れてしまった自律神経を整えてくれるのに役立つのです。
入浴する際の注意点・ポイント
入浴するときに気をつけないと、かえって交感神経が活発になってしまうことがあります。これでは寝付くのも難しくなりますし、体をゆっくりと休めることができず次の日に疲れが残ってしまいます。自律神経を整えるために入浴するのなら、次の点に気をつけましょう。
熱すぎるお湯はダメ
一般的には42℃前後のお湯を心地よい温度と感じる人が多いのですが、これは体にどのように作用するのでしょうか。熱いお湯で入浴すると体の機能が活性化され、交感神経が刺激されます。交感神経が刺激されるので、体が活動に備えて準備し、目が冴えてきます。寝る前には副交感神経を優位にすることで体を休め眠りに導くことができることを考えると、寝る前に熱いお湯で入浴するのはやめたほうがいいようです。
シャワーで済ませてしまうのもダメ
忙しいときや暑い夏は、ついシャワーだけで済ませてしまいがちですが、これも体を休めるという観点からすると、おすすめができないのです。シャワーの時は湯船よりもちょっと高めにお湯の温度を設定して、シャワーヘッドから勢いよく出てくるお湯を浴びますよね。このどちらも体に刺激となってしまい、 交感神経が活発になってしまうのです。
朝のシャワーは、交感神経を優位にして目を覚ます効果は抜群なのですが、夜のシャワーは逆に快適な睡眠を妨げてしまうことになってしまいます。夏であっても湯船につかることで、副交感神経が優位になり疲れをしっかりととってくれるので、夏バテ防止にもなるのです。
お風呂で自律神経を整えて、健康的な体に
『入浴で健康に!自律神経を整えるお風呂の入り方とは』というテーマで自律神経が乱れてしまう原因、その症状、自律神経を整える入浴方法についてご紹介しました。
自律神経が乱れると、体の様々な部位に症状が表れてしまいます。毎日の入浴方法を少し工夫するだけで、自律神経を整えることができるのですね!健やかな毎日を過ごすのに、この記事がお役に立てば幸いです。